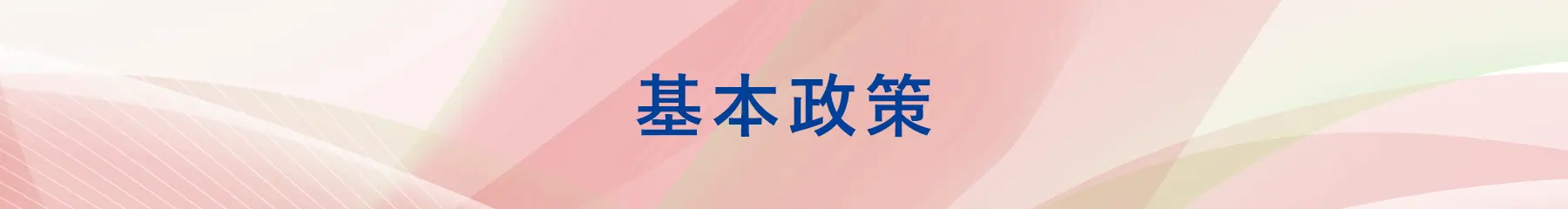

社会保障制度の充実のためにも、経済の活性化が必要です。
現在の日本は、弱肉強食である米国流の金融・経済政策原理に基づいているばかりか、実態を伴わないマネーゲームの様相を呈しており、いろいろな所で綻びが出ています。戦後の復興から経済大国へと日本の繁栄を支えてきたのは、大企業ばかりではなく、多くの中小企業の活躍、特に「モノづくり」での活躍でした。ところが、小泉純一郎首相(当時)の構造改革において、政府・与党は「大きいところは守るけれども、小さいところはご勝手に」という無責任なダブルスタンダードをとり、多くの中小企業が、不良債権処理の名目により、貸し渋り・貸しはがしをされ倒産しました。正しい政策さえあれば、元気になれる中小企業が多くあったにもかかわらず、一体何のための大銀行への公的資金(国民の皆さんの税金)投入だったのでしょうか。 多くの金融機関は、バブル期の自らの失敗のツケを国民に回し、公的資金の提供を受ける一方で預かったお金に対する利子はほとんどつけず、国から与えられた自己資本比率の目標をクリアーするために、中小企業に対する貸し渋り・貸しはがしを行ったのです。2014年10月31日、日本銀行は円を増刷して日本国債を買い支える量的金融緩和の拡大を発表しました。これまで日銀が一年間に50兆円の日本国債を買い支えてきたのを、80兆円に拡大するというものです。これは、日本政府が新規発行する国債の年間総額とほぼ同じです。日銀が国債を購入する一方で、年金基金などがその分を国内外の株式を保有することになり、一連の株価急騰が実現していますが、これは「中央銀行による国債購入」と「年金運用のリスク拡大」の二点で「禁じ手」だったのです。
金融緩和によって株価が上がる一方で、実体経済は先細っています。非正規雇用労働者の割合は2022年で36.9%に達しており、その平均年収は198万円です。この傾向を是正しなければ、日本の国内消費が冷え込むばかりであり、将来的には年金受給額の減額による高齢者の深刻な貧困が危惧されます。バブル崩壊以降、長期にわたる経済の閉塞状況の原因は、国民の所得を削り、中間層を激減させたことによる個人消費の低迷にあります。
消費性向は、所得が高いほど低い。経済のイロハのイです。中間層が減って、その分貧困層がふえれば、購買力がないために消費は減少します。高所得者だけが増えても、限界消費性向のために、消費の大きな拡大にはつながりません。
消費性向の高い、所得の低い人から所得の底上げを図る。そのことによる消費の喚起が大切です。苦しい中で頑張っている人を支えるという社会政策的観点だけではありません。消費不況を脱出し、経済と社会を活性化させるために、私たちは、分厚い中間層を取り戻すという草の根からの経済再生を進めてまいります。
そのために、ワーキングプアをなくし、安心して働き暮らすことのできる賃金を確保しなければなりません。全国どこでも誰でも時給1,500円以上になるように最低賃金を引き上げなければなりません。望めば正社員になることのできることも必要です。同じ価値の仕事をすれば同じ賃金が支払われるよう、「同一価値労働同一賃金」を実現し、ILO第100号条約の遵守を徹底します。

税は社会を動かすために必要ですが、負担できる能力に応じて徴収されていかなければなりません。しかし、現在は所得の低い人にも同じようにかかる消費税を増やし、所得の高い人の所得税、大企業の法人税が大きく引き下げられています。いま必要なのは、普通に働く人の暮らしを立て直すことです。消費税に頼るのではなく、所得税の見直しや、利益を出している法人からの税収を高め、その税収を格差是正のために配分し、低くなった労働分配率をあげていくことが必要です。中小企業には、国が社会保障料の一部を補填するなどの支援をします。最低賃金と労働生産性は相関しているため、労働生産性が上がれば、GDP1%の上昇で税収が1兆円は増えます。また給与増にともなって、国内消費が上がれば国の税収も上がります。普通に働く人々の生活を守り、ボトムアップを実行する。そのための施策を進めていきます。
日本は経済再生と財政再建を両立させなければならない難しい時を迎えています。まず日本を魅力ある市場とするための規制緩和を実現する一方、行き過ぎた投機を抑制し、公正な取引が確保されるよう、市場監視機能を高めなければなりません。同時に中小企業の権利と開発能力を高めるため、中小企業省を設置し、産官学の連携を豊かにし、資源のない我が国の利点である、人材育成に力を入れるとともに、海外からの人材の活用にも力を入れます。そして、正社員と非正社員の均等待遇を実現し、年金と健康保険の充実を図ることで内需の基盤を強化します。
農地の上で太陽光発電を行い、農地を立体的に活用し、エネルギーと作物を同時に創ることができるソーラーシェアリングが脚光を浴びています。これからのソーラーシェアリングは「食もエネルギーも地産地消」というコンセプトに基づいた自家発電・自家消費型へ本格移行していきます。ソーラーシェアリングは今の世界が抱えるエネルギー、食糧の問題を根本から解決する可能性を秘めており、これからの時代をリードする役割を果たすと考えられます。私が座長代理を務める立憲民主党環境エネルギーPTでは、産業社会のグリーン化を推進することにより、再生可能エネルギーや蓄電技術など新しい成長産業分野において250万人の新たな雇用の創出を目指しています。
立憲民主党は景気の問題は雇用の問題でもあると捉え、雇用を増やす施策と予算配分を提案しています。職業訓練には手厚い手当てをし、最低賃金の引き上げを行い、日雇い派遣を禁止します。必要なくなったムダな公共事業をカットし、福祉産業を育てることによって雇用を吸収していくのです。医療や介護を含む福祉産業あるいは、保育や教育における労働条件の改善は、サービスを受ける側にとってもプラスになり、この分野の充実と活性化が安定した景気循環をつくるのです。 今求められているものは、名ばかりの構造改革ではなく、きちんと経済を動かしていく、「ムダをなくし、必要なところに必要な配分をする」予算の構造変革であり、「お金が回る」ように、とりわけ、消費世代である若年層の人たちが「普通にやっていけば、何とかやっていける」と思える安心の社会をつくることです。
(2023年7月記)